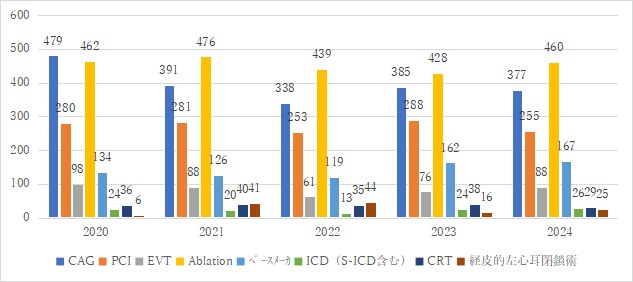循環器内科で行っている臨床研究
「持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後の不整脈再発リスクに関する研究」(単施設研究)
現状当院で施行している持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後の経過を調べることで、今後のカテーテルアブレーション治療における質の向上に役立たせることを目的としております。「循環器診療の実態調査」(多施設共同研究)
当院では、日本循環器学会が実施する全国的に循環器診療の実態調査を展開して診療実態を具体的な数で把握するためのデータベース構築として「循環器疾患診療実態調査(JROAD)」を行っています。
病名や診療行為の明細が含まれたDPCデータを集め、データベースを作成します。循環器疾患における医療の質を向上させるための基本的な資料とすることを目的としています。
※詳細はこちらをご覧ください「東京都における心血管(循環器)緊急症の実態調査」(多施設共同研究)
当院では、東京都CCU連絡協議会が実施する循環器診療の実態調査を展開して診療実績を具体的な数字で把握するためのデータベース構築として「東京都における心血管(循環器)緊急症の実態調査」の多施設共同研究に参加しています。
心血管緊急症のより良い救急医療体制と治療方法を検討し、今後の診療改善に役立てることを目的としています。「カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト(J-ABレジストリ)」(多施設共同研究)
当院では、カテーテルアブレーションによる治療の現状(施設数、術者数、疾患分類、合併症の割合等)を把握することにより、
カテーテルアブレーションの不整脈診療における有効性・有益性・安全性及びリスクを明らかにし、
更に質の高い医療を目指すことを目的とする多施設共同研究に参加しています。
※詳細はこちらをご覧ください(リンク先:J-AB公開文書)「植込み型心臓電気デバイス治療に関する登録調査」(多施設共同研究)
当院では、心臓植込み型デバイスによる治療の現状(施設数、術者数、疾患分類、合併症の割合等)を把握することにより、
心臓植込み型デバイスの不整脈診療における有効性・有益性・安全性及びリスクを明らかにし、
更に質の高い医療を目指すことを目的とする多施設共同研究に参加しています。「複数回の手術を要した心房細動に対する化学的アブレーションの有効性に対する検討」(単施設研究)
当院では、非弁膜症性心房細動に対して複数回のカテーテルアブレーション治療を要した患者さんを対象に、
マーシャル静脈に対する化学的アブレーションの有効性の検討を目的とした研究を行っています。
※詳細はこちらをご覧ください(リンク先:複数回AF説明書)「リード抜去症例の実態調査(J-LEXレジストリ)」(多施設共同研究)
経静脈的リード抜去術を受ける方を対象に、国内にどのくらいの患者さんがいるのか、どういう人がこの治療を受けているのか、
治療方法の違いなどを検証するための研究です。「経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症心房細動患者の塞栓予防の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 -J-LAAO-」(多施設共同研究)
当院では、経皮的左心耳閉鎖システムによる治療を受けた患者さんを対象に、治療前後のデータを収集し、
本治療法を安全かつ効果的な治療法として患者さんに届けることを目的とする多施設共同研究に参加しています。
本研究は、主となる日本循環器学会のほか複数の学会が協力して進めています。
詳細はこちらをご覧ください(リンク先:J-LAAO 公開文書)「日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析」(多施設共同研究)
当院では、心血管疾患に対するカテーテル治療をおこなった患者さんの治療記録を、日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)施行の症例登録システムに登録する事業に協力しています。
※詳細はこちらをご覧ください(リンク先:J-PCI)「難治性心室性不整脈に対する冠動脈分枝、冠動脈に対する化学アブレーション研究」
通常の高周波カテーテルアブレーション治療が困難な症例に対して、冠動脈分枝または冠動脈に対してエタノールを注入して治療を行います。「カテーテルアブレーション施行患者を対象としたTMDU多施設レジストリ研究」(多施設共同研究)
東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)および共同研究施設におけるカテーテルアブレーションの現状(疾病分類、合併症割合、治療経過、予後等)を解析することにより、カテーテルアブレーションの不整脈治療における有効性・有用性・安全性を明らかにすることを目的とする研究です。
※詳細はこちらをご覧ください(リンク先:カテーテルアブレーションTMDUレジストリ) 「左房内血栓症マネージメントに関する後ろ向き研究」(多施設共同研究)
※詳細はこちらをご覧ください「ウェアラブル機器を用いた不整脈診断の精度と有用性の横断的検証」(多施設共同研究)
ウェアラブル機器のアップルウォッチとフィットビットを対象として、その不整脈検知能力を評価し、現在の治療方針をより適切なものとする研究です。「心室性不整脈アブレーションにおける2本の電極カテーテルによる冠状静脈同時マッピングの有用性の検討」(多施設共同研究)
左室流出起源の心室性不整脈治療において、複数のカテーテルを用いて冠状静脈のマッピングをすることの妥当性を検討することを目的とし、その不整脈の起源をより正確に固定することで、治療効果の向上に貢献します。「持続性心房細動に対するアブレーション後の心房頻拍の再発様式に関する検討」(単施設研究)
アブレーション後の心房頻拍再発様式について検討することで、頻度を解析し、2度目のアブレーション治療の成功率の向上を目的とする研究です。「陳旧性心筋梗塞に伴う持続性心室頻拍の不整脈基質、アブレーション成績に関する多施設後ろ向き研究」(多施設共同研究)
陳旧性心筋梗塞に合併する心室頻拍に対する高周波カテーテルアブレーション治療は確率された治療法であるが、これまでの報告は欧米の患者さんを対象とした研究結果である。日本人の患者さんの情報を解析し、今後のアブレーション治療の発展につながることを目的とする研究です。「急性心筋炎の臨床的特徴と転帰の探索に関する全国規模の調査研究」(多施設共同研究)
当院では、心筋炎の重症メカニズムの解明、原疾患・患者背景による臨床的特徴の把握、疾病経過や予後の解析を進め、将来的な治療法の確立や予防戦略の構築、ひいては患者予後の改善を目指すことを目的とする多施設共同研究に参加しています。 「多摩地域における特発性冠動脈解離の発症率、治療戦略、予後に関する多施設後向きコホートレジストリ研究:Tama SCAD registry (多施設共同研究)」
当院では、突発性冠動脈解離(SCAD)の発症率、治療、予後を明らかにすることを目的とした多摩地域の多施設共同研究に参加しています。「POLARxを使用したクライオバルーンアブレーションによる食道迷走神経障害に伴う胃拡張の予測因子の検討」(多施設共同研究)
クライオバルーンを用いたアブレーションにおいて、今後の合併症(食道迷走神経障害による胃拡張)予防のために予測因子を検討します。「心房細動およびその他の不整脈に対するカテーテルアブレーションにおける肺静脈および非肺静脈に対するパルスフィールドアブレーションの有効性と安全性に関する検討」(多施設共同研究)
2024年9月に新たに導入されたパルスフィールドアブレーションは、熱伝導を介さないアブレーション方法であり、周囲の組織や血管、神経へのダメージが少ないとされています。従来のアブレーション方法と比較し、有効性と安全性を比較し検討します。「経皮的冠動脈形成術(PCI)を施行された初期心室細動(VF)波形を呈した院外心停止(OHCA)患者さんにおけるDoor-to-Balloon(D2B)時間と院内死亡率の関連に関する臨床研究:観察研究」(単施設研究)
※詳細はこちらをご覧ください「冠動脈ステント留置後の外科手術周術期におけるアスピリン継続の有用性を検証する多施設ランダム化比較試験(OPERATION)」 (多施設共同研究)
冠動脈ステント留置を受けた患者さんでは3年で20%以上の方がなんらかの外科手術を受けられており、外科手術の際に抗血小板剤をどのようにするのか明らかにするのは非常に重要と考えられます。
以上の点をふまえ、外科手術に際してアスピリンを直前まで継続して手術を受けた場合と、術前に抗血小板剤を中断して手術を受けた場合の有用性と安全性を比較検討します。
お知らせ
患者さんを診療する上で用いた検査・治療のデータを症例報告、臨床研究等に利用させて頂くことがあります。 この場合、お名前・ご住所など患者さんを特定できるようなことは一切ありません(匿名化といいます)。本研究への参加を拒否することもできます。 上記に該当される患者さんで参加を希望されない場合や、ご質問があれば主治医にお尋ねください。参加を希望されなくても診療上患者さんの不利益になることは一切ありません。 ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。